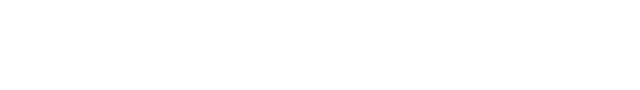一口の大きさで太りやすさが変わる!?大阪大学の研究からわかること
「早食いは太りやすい」という話を耳にしたことがある方も多いでしょう。しかし、最近の大阪大学の研究によって、「一口の大きさ」が肥満に与える影響が明らかになりつつあります。この新たな知見は、食習慣の改善に向けた重要な指針となるかもしれません。
一口の大きさと肥満の関係
大阪大学大学院歯学研究科の山本梨絵博士が主導した研究では、成人202名を対象に、食事中の「一口の大きさ」と肥満度(BMI)や内臓脂肪レベルとの関連を調査しました。その結果、食事中の「総口数」がBMIや内臓脂肪レベルと正の相関を示すことがわかりました。つまり、一口の量が多いと、肥満のリスクが高まる可能性があるということです。
速食いと肥満の関連
また、研究では「速食い」と「総咀嚼時間」の関係も明らかになりました。速食いをする人は、咀嚼時間が短くなる傾向があり、この速食いが肥満の一因となる可能性が示唆されています。つまり、食べる速度が速いと、満腹感を感じる前に食べ過ぎてしまい、結果として肥満につながる可能性があるのです。
研究の背景と社会的意義
世界的に肥満人口が増加しており、日本でも成人の肥満率が高まっています。肥満は、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病のリスク因子とされています。そのため、肥満予防のための新たなアプローチが求められています。
これまで、食事の内容や運動量が肥満に影響すると考えられてきましたが、今回の研究は「食べ方」や「咀嚼の仕方」が肥満に関連している可能性を示しました。この新たな視点は、肥満予防や改善のための食事指導において、重要な要素となるでしょう。
実生活への応用と今後の展望
研究者たちは、食事指導において「一口の大きさ」や「咀嚼の時間」に焦点を当てることの重要性を指摘しています。具体的には、一口の量を小さくし、ゆっくりと時間をかけて食べることで、満腹感を早く感じ、食べ過ぎを防ぐことが期待されます。
今後は、これらの知見を基にした食事指導プログラムの開発や、咀嚼を促進するための食品の開発が進められることが期待されます。また、咀嚼の回数や時間を簡便に測定できるデバイスの開発も、肥満予防の新たな手段となるかもしれません。
まとめ
大阪大学の研究により、「一口の大きさ」や「咀嚼の仕方」が肥満に影響を与える可能性が明らかになりました。これらの知見は、食習慣の改善に向けた新たな指針となるでしょう。日々の食事において、一口の量を適切にし、ゆっくりと噛んで食べることが、健康維持に繋がることを意識してみてはいかがでしょうか。
札幌 歯周病・予防歯科 院長
歯周病治療および予防歯科を重視し、口腔の健康を目標とした治療を心がけています。
- 日本歯周病学会指導医
- 日本臨床歯周病学会指導医
- 日本糖尿病学会協力歯科医
- 日本歯周病学会認定研修施設
プロフィールはこちら